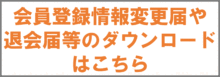調査・研究事業報告一覧(各リンクをクリックすると該当の報告書ダウンロード先へ移動します)
【令和4年度老人保健健康増進等事業】
・認知症高齢者グループホームの令和3年度介護報酬改定の施行後の状況に関する調査研究事業報告書
【令和3年度老人保健健康増進等事業】
・認知症高齢者グループホームの令和3年度介護報酬改定の施行後の状況に関する調査研究事業報告書
【令和2年度老人保健健康増進等事業】
・認知症高齢者グループホームにおける介護サービス提供の実態に関する調査研究事業報告書
【令和2年度老人保健健康増進等事業】
・地域における認知症ケアの拠点としての認知症高齢者グループホームでの適切な相談支援に関する調査研究事業報告書
【令和元年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおける効果的な従事者の負担軽減の方策とグループホームケアの効果・評価に関する調査研究事業
【平成30年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおけるケアの効果・評価に関する調査研究事業
【平成29年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおけるグループホームケアの効果・評価に関する調査研究事業
【平成28年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおける運営推進会議および外部評価のあり方に関する調査研究事業
【平成27年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業
【平成26年度老人保健健康増進等事業】
・地域包括ケアシステムにおける認知症ケア相談・支援事業推進における認知症グループホームの活用・機能強化に関する調査研究報告書
・認知症グループホームの強みを活かして!~グループホームの多機能化に向けた手引き(パンフレット)
【平成25年度老人保健健康増進等事業】
・地域包括ケアシステムにおける認知症グループホームの役割と多様化に関する調査研究報告書
【平成25年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームを拠点とした認知症の人や家族支援のあり方に関する調査研究報告書
【平成24年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおける利用者の重度化の実態に関する調査研究報告書
【平成24年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおける災害時対策に関する研究報告書
【平成23年度老人保健健康増進等事業】
・グループホームにおける災害時対策に関する研究報告書
・(別冊)東日本大震災 被災グループホームに学ぶ
【平成23年度老人保健健康増進等事業】
・グループホームの生活単位が及ぼすケアの質への影響に関する調査研究報告書
【平成23年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームの質の尺度と自治体における活用に関する調査研究報告書
・(別冊)認知症グループホームの手引き
【平成22年度老人保健健康増進等事業】
・グループホームの安全性確保・向上に関する調査研究報告書
【平成22年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームにおける多機能化と今後の展開に関する調査研究事業報告書
【平成22年度老人保健健康増進等事業】
・認知症の人の暮らしを支えるグループホームの生活単位のあり方に関する調査研究事業報告書
【平成21年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホーム実態調査事業報告書
【平成21年度老人保健健康増進等事業】
・認知症グループホームの将来ビジョン2010
【独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」助成事業】
・認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業
・認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック
【平成20年度老人保健健康増進等事業】
・認知症GHにおける重度化対応と医療連携に関する調査研究報告書
【平成20年度独立行政法人福祉医療機構「長寿・子育て・障害者基金」助成事業】
・認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業
【平成18年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金】
・認知症グループホームにおける虐待防止・権利擁護研究事業
【平成18年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金】
・認知症グループホームにおける看取りに関する研究事業
【平成18年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金】
・認知症グループホーム事業実態調査・研究事業
令和4年度老人保健健康増進等事業
認知症高齢者グループホームの令和3年度介護報酬改定の施行後の状況に関する調査研究事業報告書
令和3年度老人保健健康増進等事業
認知症高齢者グループホームの令和3年度介護報酬改定の施行後の状況に関する調査研究事業報告書
令和2年度老人保健健康増進等事業
認知症高齢者グループホームにおける介護サービス提供の実態に関する調査研究事業報告書
令和2年度老人保健健康増進等事業
地域における認知症ケアの拠点としての認知症高齢者グループホームでの適切な相談支援に関する調査研究事業報告書
令和元年度老人保健健康増進等事業
認知症グループホームにおける効果的な従事者の負担軽減の方策とグループホームケアの効果・評価に関する調査研究事業
事業結果の概要
報告書(11MB)
認知症グループホームケアのエビデンス ~ BPSDの低減とQOLの向上~
平成30年度老人保健健康増進等事業
認知症グループホームにおけるケアの効果・評価に関する調査研究事業
事業結果の概要
報告書(10MB)
地域貢献尺度(事業所評価)・地域交流尺度(入居者評価)
平成29年度老人保健健康増進等事業
認知症グループホームにおけるグループホームケアの効果・評価に関する調査研究事業
報告書の訂正について
事業結果の概要-訂正版
報告書-訂正版(8MB)
平成28年度老人保健健康増進等事業
認知症グループホームにおける運営推進会議および外部評価のあり方に関する調査研究事業
平成27年度老人保健健康増進等事業
認知症グループホームを地域の認知症ケアの拠点として活用するための調査研究事業
地域包括ケアシステムにおける認知症ケア相談・支援事業推進における認知症グループホームの活用・機能強化に関する調査研究報告書
本研究では、グループホームにおける相談・支援の状況について、量的、質的調査によって明らかにするとともに、平成27年度から地域支援事業における認知症地域支援・ケア向上推進事業に位置づけられることも踏まえ、調査結果をもとにパンフレットを作成し、事業者、自治体にその普及啓発を図ることを目的として実施した。
本調査では、地域支援活動の主な内容として、①「認知症の啓発活動」、②「相談支援」、③「居場所づくり」の3つに焦点を当てて、アンケート調査、ヒアリング調査を実施し、調査結果をもとに、今後、グループホームが地域に向けた事業展開を効果的に進めていく上での取組みのポイントについて、以下の3点に整理した。
① 想像力とアイディアを活かす
(人を呼び寄せる・巻き込む、入居者も職員も楽しく過ごせるように考える、職員の意見に耳を傾ける・裁量権を与える)
② 外部資源とのネットワークを広げる
(グループホームの認知症ケアを知ってもらう、場所の確保や協力者を集める、情報をつなぐ・人をつなぐ)
③ 「おたがいさま」の関係づくりを目指す
(顔の見える関係と相談しやすい雰囲気をつくる、「支えている」と「支えられている」を意識する、地域の応援団とつながる・増やす)
また、調査結果から明らかになったことは、グループホームの多機能化や地域に向けた事業展開は、決してグループホームの負担を強いるだけの取り組みではなく、メリットしてとらえることもできるという点である。グループホームのメリットについては、①社会的な価値・信頼度の向上、②利用者の暮らしとリスク管理、③人材確保・育成と離職の防止、④経営的な側面の4点に整理をした。
認知症グループホームの強みを活かして!
~グループホームの多機能化に向けた手引き(パンフレット)
地域包括ケアシステムにおける認知症グループホームの役割と多様化に関する調査研究報告書
本研究事業においては、昨年度研究事業の調査結果を踏まえつつ、地域包括ケアシステムにおける認知症グループホームの基本的役割を明らかにするとともに、「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」推進の観点から、認知症グループホーム運営の多様化の実態把握、及び運営上の課題についての集約を図ることを目的として実施した。
本調査では、地域包括ケアシステムの中でグループホームに要請されている「①相談支援機能」「②個別ケアの資質向上のための機能強化」「③地域との密な連携」「④医療機能の確保・強化」の4つの役割・機能について確認し、その役割・機能を確保するために各事業所がどのように取り組んでいるかの確認を行った。
寄せられた多くの事例からは、多くの事業所が4つの全て、または複数分野に対して取り組んでおり、認知症の人の生活を支えるべく、グループホームが高齢者のライフステージの変化に合わせた機能を新たに持ちつつあることが確認できた。
「②個別ケアの資質向上のための機能強化」の追求は、全グループホームが取り組むべき課題として認識し、実践しているものと考えられる。その上で、グループホームの背景や経緯、地域ニーズや地域資源の状況等を勘案しつつ、地域包括ケアシステムの中で、「①相談支援機能」「③地域との密な連携」「④医療機能の確保・強化」に取り組んできているものと考えられる。
認知症グループホームを拠点とした認知症の人や家族支援のあり方に関する調査研究報告書
本研究事業においては、今後におけるグループホームの新たな展開の可能性を探るべく、在宅の認知症の人やその家族への支援のあり方について先駆事例の調査ならびに事例収集と今後の方向性に関する考察を行った。
(1)地域支援におけるグループホームの役割
地域支援におけるグループホームの取組みからは、①地域の介護拠点としての機能を発揮すること、②認知症の啓発活動に取り組むこと、③個別の人が必要とする支援に「つなぐ」機能を果たすこと、そして、④認知症の人やその家族のより所となるような「居場所」をつくること、などの具体的な活動内容が見えてきた。これらは、単体としてのグループホームに止まらず、認知症カフェ等を含む地域支援(事業)に積極的に取り組んでいく意義を明らかにするものである。
(2)認知症カフェの類型と運営のポイント
「居場所づくり」の現状を踏まえて、その運営形態をあえて類型的に分析するならば、①ミニ・デイ型、②コミュニティ・カフェ型、③目標志向性の強い福祉サロン型、④貸館利用型、4つの傾向を読み取ることができる。また、上記に共通する運営のポイントは、主に①場所の確保、②人材の確保、③スタッフ教育、④地域住民への啓発活動、⑤アイディア、⑥外部資源とつながるネットワーク力、の6点が挙げられる。
(3)考 察
現時点において、「認知症カフェ」等は、限られた地域の限られた事業所による小規模な展開となっていることは否めない。しかし、今後、認知症の早期診断・早期対応が進み、若年性の認知症の人びと、軽度認知障害(MCI)レベルの人など、地域の多様なニーズとその増加を想定すれば、この「認知症カフェ」事業が地域で開設から順行運営されることが必須になってくるだろう。さらに発展的見通しを想定する際には、市町村による地域支援事業としての位置づけ・財政支援が不可欠である。他方、早急に事業の枠組みが定められる必要があり、また、地域の特性を生かした取組みが期待されている。
認知症グループホームにおける利用者の重度化の実態に関する調査研究報告書
本研究事業は、認知症グループホームにおける利用者の重度化について概念整理をしたうえで、基礎的データを多角的に収集し、クロス集計などの分析により、その実態について明らかにするとともに、そこから導き出される特徴的な事例について事例調査を行い、その内実についてより深めていくことを目的として実施した。
本調査では、認知症グループホームにおける利用者の重度化の実態、および重度化に対応する事業所側の運営の影響についてアンケートや事例から調査した。アンケート調査からは、多くの事業所において利用者の重度化が進んでいる傾向がみられ、重度化が進む利用者のニーズを踏まえ、多くの事業所が医療処置や看取り等にも対応できるよう人員体制の整備等に努めている傾向が明らかとなった。また、事例調査からは、全国各地の事業所で、様々なタイプの重度な利用者に対し、その人に合ったケアに献身的に取り組まれていることも明らかとなった。
利用者の重度化の傾向としては、①老化に伴う心身の虚弱化、②認知症の中核および周辺症状の進行、③医療ニーズの高まり等によって、重度化が進行し、最終的にはターミナル期の対応が求められている。一方、これら重度化の諸要因は、並行して展開されることも多く、特に支援課題がどの側面に因っているのか等、対応のポイントが異なり、具体的かつ適切な対応方法は多様であることが明らかになった。
認知症グループホームにおける災害時対策に関する研究報告書
本研究事業は、昨年度当協会が実施した災害研究の調査結果と被災地二年目の調査結果等を踏まえて、災害時介護派遣チーム(DCAT)の創設と認知症グループホームにおける事業継続計画(BCP)の構築の2つの視点から考察を行い、地域包括ケアシステムを見据えたまちづくりにおける認知症グループホームの役割について、より具体的な観点から災害対策の重要性を訴えていくことを目的として、以下の4つのテーマを中心に実施した。
(1)災害支援活動の実態から見えてきた課題整理
①事業者間における平時からの関係づくり、②災害直後の急性期における災害介護派遣チームの必要性、③急性期に続く継続的な介護派遣チームの必要性、④コーディネーター機能の充実、⑤災害時にも迅速に機能発揮ができる人材育成のあり方、等の観点から今後の取組み課題を明らかにした。
(2)災害支援体制(災害ネットワーク)の構築
迅速かつ効果的な災害支援に向けての在るべき姿(方向性)として、重層的ネットワークの構築のあり方、ならびにそのネットワークを機能させていくコーディネーターの具体的な役割・機能をまとめた。
(3)災害介護派遣チームの組成について
災害発生直後から2カ月程度の混乱期において活動する派遣チームを「災害介護派遣チーム」、その後、継続的に介護の支援活動を行う派遣チームを「継続介護派遣チーム」として定義し、これらのチームの活動においてどのような点に留意すべきかを整理した。
(4)グループホーム災害対策研修プログラムの策定
東日本大震災で被災したグループホームの災害対策、避難行動やその後の避難生活における困難さ、事業継続の苦労、外部からの支援体制のあり方、災害時における認知症ケアのあり方などを「DVD・訪問調査記録(平成23年度事業)」から学び、自らの事業所の災害対策に活かすことを目的とした研修プログラムを紹介した。
グループホームにおける災害時対策に関する研究報告書
東日本大震災は、非常時におけるさまざまな課題を浮かび上がらせた。被災した事業所の災害対策のあり方、早期の外部からの支援体制のあり方、情報発信や情報共有のあり方、ネットワークを活かした緊急介護活動、資源・物資の調達・配送方法など、大災害に対応するには常日頃からそれを想定し、対応策を用意しておく必要がある。また、自分自身が被災者でもある多くの職員が、過酷な環境の中で介護業務に携わり、利用者の命と生活を守ろうと奮闘しつつ、心身ともに負担を蓄積させていく実態からは、職員の支援について課題が浮き彫りとなった。
本研究事業では、人智を超えた災害直後からの支援方法や、認知症の人やその家族を支援する介護事業者のネットワーク活動、情報共有のあり方について整理する。さらに、災害時における認知症ケアの課題や支援のあり方を取りまとめ、今後、災害が起きた場合の緊急時支援対策として、全国の自治体や協会支部、個別事業所等に情報を提供することをねらいとしている。また、介護支援体制の構築や、災害対策マニュアル策定など、今後に役立てていくことに寄与していきたい。広範囲にわたる緊急事態では、起こりうるあらゆる事態を視野に入れ、災害時の対応策を整備することが望まれるところである。
本調査研究では、認知症グループホームにおける災害時対策について、被災の事実を検証したうえで、「備え」「建物・環境」「支援体制」「期待される役割」という4つの視点から考察を行うこととした。また、同時に映像教材を制作し、事実を記録にとどめ、より具体的な観点から災害対策の重要性を訴えていくこととする。
東日本大震災 被災グループホームに学ぶ
公益社団法人日本認知症グループホーム協会は、平成23年度老人保健健康増進等事業により、「グループホームにおける災害時対策に関する研究事業」に取り組んできました。この冊子は、平成23年6月26日~28日にかけて宮城県、岩手県沿岸部のグループホームを訪問し、被災者の皆様から聞かせていただいたさまざまな体験や意見を記録として残したものです。本研究事業の取り組みとして作成した研修用DVD「東日本大震災 被災グループホームに学ぶ」と合わせて、グループホーム管理者等の方々から聞こえてくる声に耳を傾け、今後の災害対策に役立てていただければ幸いです。
グループホームの生活単位が及ぼすケアの質への影響に関する調査研究報告書
本事業は、日本認知症グループホーム協会が平成21年度に実施した「認知症グループホームのあり方の研究事業(報告書名:「認知症グループホームの将来ビジョン2010」)において示唆された、グループホームの生活単位(1ユニット当たりの利用者人数)の適正化への提案や、サービスを展開する上での方向性などについて、昨年度の「認知症の人の暮らしを支えるグループホームの生活単位のあり方に関する調査研究事業」の流れを受けて行ったものである。認知症ケアでは、「なじみ」や「寄り添う」という言葉が盛んにつかわれている。確かに、認知症の人が安心して暮らせる環境を整えるために、グループホームに入居された後であっても、その人がこれまでなじんできた環境を維持し、一人ひとりの要望に応じたアクティビティを行うなど、利用者に寄り添うケアを行うことは重要である。
しかし、そういったケアを提供するための利用者定員や職員配置は、どのようであるべきかという議論は、これまであまりなされておらず、職員や管理者の資質や個々の事業所の取り組みに任せてしまっているところが大きい。また、今後認知症高齢者の数が激増することが予想されるなか、認知症ケアの最先端を担うグループホームのケアが、日本の認知症ケア全体の指針となっていくことが期待される。そのため、グループホームにおける「ケア」とはどうあるべきか、認知症ケアに対するどのような姿勢や事業所運営が望まれるのかといったことを明らかにしていくことが、認知症の人の尊厳を支えるケアには必要であろう。本協会ではこれまで継続的にグループホームのサービスの質の向上に取り組んできたが、今年度は昨年度に引き続き、認知症の人の安心と尊厳を保つケアを実践するための、適切な生活単位についての議論・検証を行うと同時に、グループホームにおける調査研究を基にした提言を行うこととした。
認知症グループホームの質の尺度と自治体における活用に関する調査研究報告書
地域密着型サービスの普及・推進において、市町村は、サービス提供事業者(以下事業者という)の選定・指定、実地指導、指定更新などの機会を通じて、良質な事業者を見極めたり、育てたりしていく責務を担っている。その対応においては、基準省令に関わる違反の有無だけでなく、ケアサービスや事業運営の適正を見極め、認知症ケアや地域密着型サービスの本質を踏まえた指導・監督が求められている。
しかし、地域のケアサービスの質をいかに担保していくの方法は、それぞれの自治体によって様々であり、ケアサービスに対する指導内容も、考え方もそれぞれである。また、市町村職員の人事異動が一定のサイクルで行われる現状において、担当者自身が地域密着型サービスや認知症ケアの本質を理解し、ケアサービスの良し悪しを判断するだけの力量を備えることは容易ではない。そのため、事業者との想いと、行政との想いとの間とのギャップや実地指導の際の軋轢などが生じてしまう面もある。本調査研究事業は、各々の地域が認知症ケアの質を高め、良質な事業者を育てていくために、本来、グループホーム等の地域密着型サービスに求められるケア質とは何かを、認知症の人の生活支援の視点から問いかけていく。
また、ケアサービスに対する、事業者、市町村、利用者・家族、地域住民、外部評価機関等、それぞれの人の価値観を合わせながら、地域全体で認知症の人を支えていく地域づくり、体制づくりに寄与する情報提供を行う。
認知症グループホームの手引き
この手引書は、グループホームや小規模多機能型居宅介護など、地域密着型サービス事業所を運営する事業者の皆さん、ならびにこれから事業所の指定および指導監査を担当する市町村の行政職員の皆さんが、認知症ケアに関する介護現場の取組や関連する施策の動向について振り返る際の参考資料としてご活用いただくことを意図してまとめたものです。
認知症ケアを担う地域密着型サービス事業所の皆さんにとっては、新人スタッフの育成やケアの質の向上について考える際のきっかけとして、また行政職員の皆さんにとっては、認知症ケアに関連する制度・施策への理解を深めるための参考資料として、この手引き書を役立てていただくことを願っています。
グループホームの安全性確保・向上に関する調査研究報告書[PDF]
2005年と2010年に発生したグループホームの火災では、多くの利用者の命が奪われる結果となった。二度と火災を起こさないことを目的に、事業所設備や消防に関わる管理・運営体制に関して規制等の強化が図られ、利用者が安全に暮らすことのできる環境が整えられつつある。
しかしながら一方で、認知症の人の尊厳のある暮らし方やグループホームが積み上げてきた認知症ケアの理念・実践が、規制によって損なわれることのないよう、十分は検討・対応を求める声が高まっているのも事実であり、実践現場のよりいっそうの努力が求められるところである。 認知症の高齢者が暮らすグループホームの防火安全を考える時、私たちは何を基準に対策を講じていくべきだろうか。 消防計画や日常的な火気管理などをマニュアル化していくことは、もちろん大切なことだが、これらは、実態に即した実践的なものでなければ意味をなさない。また、生活から火を遠ざけることばかりに集中すると、グループホームの暮らし自体が、必要以上に管理的になったり、非日常的な環境になったりする危険もある。
本調査研究は、グループホームが地域密着型サービスならではの防火安全対策を講じていけるよう、事業所運営に関わる具体的な対応策や職員の知識向上、運営推進会議、火災避難訓練の効果的な実施方法などについて、普及・啓発していくことを目的にして進められた。
認知症グループホームにおける多機能化と今後の展開に関する調査研究事業報告書
グループホームを「多機能化」という側面から振り返ると、2006年の介護保険制度改正で、短期利用サービス(ショートステイ)や共用型認知症デイサービスの提供が可能となった点が、グループホームの大きな出来事として挙げられます。
しかし、こうした取り組みが進められるにつれ、グループホームにおける「多機能化」という言葉は、短期利用や認知症デイといった制度的側面からのみ捉えられてしまいがちになり、本来の取組みの意義をグループホームに浸透させるには至りませんでした。 本研究会の課題意識は、長い間グループホームが唱えてきた「利用者の住み慣れた地域での継続的な暮らしを支える」という言葉を形骸化させず、地域密着型サービスの本来の意義を果たしていくために、グループホームが、柔軟で即応性のある支援力と認知症ケアの専門性を活かし、地域拠点として成長していくことにあります。
そのためには、日々の実践で積み重ねてきた取り組みの一つひとつを拾い集め、検証しながら、利用者が生活の広がりを持って生きていくことや、地域ニーズにどう応えていけるかの役割・機能について、理論化したり言語化したりすることが必要だと考えています。なぜなら、グループホームに携わる事業者の中でも、自分たちのサービスがになうべき役割・機能に関する認識が統一されておらず、また、利用者・家族、地域住民側でも、なにをどこまで期待してよいのかの理解が共有化されていないからです。
もちろん、こうした柔軟で即応性のある支援を支えていくためには、制度や基準のあり方を根底から見直していく必要があります。本調査研究では、まず、利用者・家族・地域がグループホームに求めているものや、これからのグループホームが利用者に向けてどんなサービスを提供していけるのかといったビジョンを明確にし、それを後押しするフレーム作りや制度のあり方について考えてみたいと思います。
認知症の人の暮らしを支えるグループホームの生活単位のあり方に関する調査研究事業報告書
本調査研究は、日本認知症グループホーム協会が平成21年度に実施した「認知症グループホームのあり方の研究事業(報告書名:認知症グループホームの将来ビジョン2010(以下、「グループホームの将来ビジョン」という))」において示唆された、グループホームの生活単位(1ユニット当たりの利用者人数)の適正や、今後、サービスを地域に展開する上での方向性などについて、前年度研究の一部を引き継ぐ形で実施した。
「グループホームの将来ビジョン」に示された課題とは、小規模で家庭的なグループホームの生活単位の見直しや、経営規模と生活規模との分離によるグループホームの新たな地域展開などである。介護保険制度施行後十年が経過して、介護サービスをとりまく環境は大きく変化している。当初、小規模で家庭的なケアサービスを前面に掲げて地域展開を進めてきたグループホームであるが、、総量規制による新設への抑圧がある一方で、都市部を中心に3ユニットの運営が認められるようになるなど、目まぐるしい方向転換に実践現場は困惑するばかりである。さらに、地域主権改革の推進が図られる中、グループホームの多床室化や中規模施設化が危惧される状況も生じてきており、グループホームにおける環境づくりや生活支援のあり方も含めて、「地域の中で人の暮らしを支える」ということの意味を、改めて見つめ直す時期を迎えている。本調査研究は、認知症の人の安心と尊厳を保つケアを実践するための、適切な生活単位や建物環境のあり方について、議論・検証を試みたものである。
生活環境、日常生活、地域交流、経営的側面等を、1ユニット5~6名で運営するグループホームと、それ以外のグループホームとで比較しながら、例えば、定員6名×3ユニット(現行の1事業所18名規模と変わらず)の生活単位で運営することのメリット、デメリットを明らかにするとともに、今後のグループホーム運営や地域展開の方策について考察する。一方で、規模の縮小化による経営面でのデメリットとの折り合いをつけていく方法にも着眼し、小規模の弱みを強みにかえていくための方法論についても検証する。
認知症グループホーム実態調査事業報告書
1990年代に登場したグループホームは、介護保険制度で「痴呆対応型共同生活介護事業」として認められて以降急増し、現在は1万事業所を越えるまでに至りました。2006年の介護保険制度改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられ、サービスは中学校区の範囲を基本としていることから、全国の中学校の数(10,864ヵ所)とほぼ同数のグループホームが存在していることになります。
このような情勢の中、事業者の経営実態、入居者本人の満足度、家族の意識、現場スタッフのやりがい、労働環境、リスク管理等、根拠に基づいたグループホーム業界全体の実態把握と構造分析が急務であるという強い認識から、日本認知症グループホーム協会では、2005年度より厚生労働省の老人保健健康増進等事業補助金を受け、「認知症グループホームの実態調査」を継続的に実施しています。
今回2009年度調査は、5年目となりますが、次期介護保険制度改正に向けた議論の重要な時期でもあることから非常に重要であると認識しています。 本研究の調査対象は、事業所調査2,140事業所(協会会員事業所)、入居者個別調査は協会会員事業所の全入居者、職員個別調査は1事業所あたり5名とし、2010年1月に郵送でアンケート調査を実施しました。
回収率は、事業所調査45.7%、職員調査44.7%と過去5年間で最も高く、会員事業所の関心度・期待度の高さが感じ取れます。特に、入居者個別調査では、8,312件の調査票を回収させていただき、非常に貴重なデータとなりました。
認知症グループホームの将来ビジョン2010
グループホームは新時代における高齢者に対する生活支援形態の新しい一手である。もうこれが決まり手であると言えよう。もともと福祉サービスは地域を見通した視点を持って企図されなければならなかったのに、われわれ福祉の研究者は地域の力を見損なっていた。その代わりに何をしていたかといえば、施設の中のケアのありようや、「世話係」としてどうあらねばならないか、といった姿勢や技法に拘泥していたといわなければならない。
それは地域から切り離された施設という密室状況の中での、援助者のあり方に限定されていた。職員は苦労しながら、限られた範囲の中で、社会資源を見つけ、苦闘を重ねるという方向でしか成果を上げられなかった。時には本人当事者の主体性を置き忘れたまま事態の推移だけを追っていたのかもしれない。
新しい高齢者ケアを牽引するグループホームは、「制度として地域に生まれたのではなく、家族や本人、医療・介護の関係者が、高齢者の尊厳を支えるという理念に培われながら築きあげてきたケア」の結晶としてのサービス形態なのである。
本報告書は、認知症高齢者支援のいわば結論としてのグループホームを、著者たちが創意を持って経験した経緯の貴重な記録である。長期にわたる時間と経験の結実として、この思想そのものの結晶を生み出したのである。この報告書を読む者は一様に今後の職業人生の助言として、これを自らの内に蓄えることができるであろう。
運営推進会議の実態調査報告書
平成18(2006)年よりより、認知症高齢者のグループホームが地域密着型サービスの一つに体系化され、2カ月に1回「運営推進会議」を開催することが義務化された。今年度の本研究では、「運営推進会議」の開催状況とその効果についてのアンケート調査と9カ所のグループホームの訪問調査を行い、認知症グループホームにおける「運営推進会議」の開催についての課題を明確にするとともに、運営推進会議ガイドブックを発行して「運営推進会議」の開催と会議の定着を目指した。
昨年度の本研究において、認知症高齢者のグループホームにおいて「運営推進会議」を開催することにより、次のいくつかの機能を果たすことになることが明確になった。その機能には①情報提供機能、②教育研修機能、③地域連携・調整機能、④地域づくり、資源開発機能、⑤評価機能がある。特に、ここでは、③地域連携・調整機能、④地域づくり、資源開発機能について取り上げる。
それは、認知症高齢者だけではなく、だれでもが安心して暮らす地域(まち)を創っていくことが究極の目標になっていくからである。
認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック
誰もが老いることを避けることはできません。そして、誰もが「老いても住み慣れた地域で安心して暮らし続けたい」と願っています。しかし、住み慣れた地域での継続的な暮らしという当たり前の願いさえも、実現するのは難しい時代になってきています。平成18年より地域密着型サービスに類型化された認知症グループホームは、介護保険制度改正とともに2ヶ月に一度の「運営推進会議」の開催が義務付けられるようになりました。
この「運営推進会議」は、グループホームのスタッフ、利用者、家族などの当事者だけでなく、地域の町内会、自治会、老人クラブ、民生委員、市町村職員、地域包括支援センター、ボランティア、消防署職員など、多くの地域関係者が集い、交流する「場(トポス)」として捉えることができます。「運営推進会議」では、グループホームの活動の紹介や認知症の理解を深めてもらうための勉強会、地域との協働による防災訓練の準備、地域全体の高齢者の問題や課題の検討など、さまざまなテーマで話し合いが行われています。
しかし、この会議で最も大切なことは、グループホームと地域とが「つながる」という事ではないでしょうか。そして、グループホームを地域に根付かせ、そのグループホームが地域の「場(トポス)」になっていくことなのです。
こうした関係性を糧にしながら、グループホームに暮らす高齢者は、地域の中でその人らしい豊かな暮らしを取り戻していくことができます。
私たちは、この「運営推進会議」に、①情報提供機能、②教育研修機能、③地域連携・調整機能、④地域づくり。資源開発機能、⑤評価機能という5つの機能があると考えています。
グループホームの活動が「地域につながる」ためにも、多くの方にこのパンフレットを活用していただき、運営推進会議のさらなる充実を図っていただきたいと思います。そして、認知症グループホームがより豊かな生活支援を実践し、豊かな地域づくりを展開していけることを期待しています。
認知症GHにおける重度化対応と医療連携に関する調査研究報告書
本調査研究事業は、2006年度から2007年度に実施した「認知症グループホームにおける看取りに関する研究事業」の継続研究事業として取り組まれたものである。
グループホームでは、利用者の初期から終末を支える地域密着型サービスとして、“重度化対応”や“看取りへの支援”が重要な課題となっているが、平成20年度のグループホーム実態調査結果などをみると、これまでにターミナルケアの実施経験を持つ事業所は37%程度にとどまり、2割強の事業所では「ADLのレベルが高い利用者を中心にサービスを提供していくべき」との考えを持っている。
また、1割程度の事業所からは、「重度化した利用者はなるべく退居してもらうようにしている」との回答が寄せられている。本調査研究事業は、より多くのグループホームが終末期支援の実践に取り組めるようにとの思いから、1年目に、医療連携、職員体制、スタッフの技術向上、健全な経営基盤などの側面による課題の検証を行い、2年目に、ターミナルケアの具体的な実践力を高めるための取り組み指針(領域1.本人・家族の想いの把握と意向の確認、領域2.医療連携、領域3.支援体制整備とチームケア、領域4.関わりのケア(コミュニケーション)、領域5.家族支援)を示したところである。
療養病床の再編に伴い、今後、さらにグループホームの重度化やターミナルケアのニーズが高まることは必至である。本稿は、事業者等が望むと望まないに関わらず、成し遂げなければならない重度者やターミナル期のグループホームケアについて、これまで指摘されてきたいくつかの問題点・課題に焦点をあてながら、制度・政策への提言をとりまとめた。
認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調査・研究事業
認知症グループホームは、2006年の介護保険法改正に伴い、地域密着型サービス類型に位置付けられ、利用者、地域住民、利用者家族、市町村職員等で構成される運営推進会議を2カ月に1回開催し、地域に開かれたサービスの質の向上・透明な運営の確保を図ることが義務付けられた。
制度施行後2年を経過し、9,900を超える事業所において年6回開催される運営推進会議の運営実態を調査士、併せて保険者である市町村及び特別区においてどのような支援、関わりを行っているかの実態を調査する。
運営推進会議の目的、会議の構成員、取り組み、地域とのかかわり、行政のかかわりなどを検証し、運営推進会議の価値、有効性をえび伝ストをもとに実証し、認知症グループホームに必要とされるサービスの質の向上・透明な運営の確保を図ることにより、認知症高齢者の尊厳ある生活を実現するために、グループホーム、行政、住民も含め、全てが共有できる運営推進会議のあり方を提言する事を目的とする。
また、本調査研究は、運営推進会議を通してグループホーム、市町村及び特別区の実態把握を行うとともに、「生活の継続性」「そのひとらしさ」「尊厳の保持」「共にある新しい地域の創生」といった理念が、日々のかかわりの中で活かされるための実践麓を紹介することにより今後の地域福祉実践についてのあり方を提言するものである。
認知症グループホームにおける虐待防止・権利擁護研究事業
2006年4月、家庭や施設で介護を受けている高齢者を虐待から守るための初めての法律として、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行された。
しかし、メディアや事例報告会などを通じた高齢者の権利侵害や虐待などの報道、報告は後を絶たず、実践現場への早急な理解浸透と徹底した対応を促していくことが必要となっている。また、小規模で限られた人材により認知症のお年寄りに向き合い支援するグループホーム・ケアの質を保証し、運営リスクの継続的な点検を行うことは、グループホームの社会的な信頼獲得や利用者および家族への安心を提供する上で、重要な取組みとなる。
本調査研究は、高齢者の権利利益の擁護に資するためのグループホーム・ケアの実態把握を行うとともに、「普通の暮らし」「一人ひとりの尊重」「尊厳の保持」といった理念が、日常ケア場面で生きた言葉として活かされるための啓発活動を実施するものである。
認知症グループホームにおける看取りに関する研究事業
グループホームは、介護保険制度施行当初から認知症ケアの切り札として常に注目を浴びてきたが、経過とともに入居者の状態は変化しつつある。比較的にADLが軽度な認知症を伴うお年寄りを対象としたサービスと謳われてきたものの、軽度で入居した利用者の身体状況は確実に重度化しており、住み慣れた地域で初期から終末までの継続的な支援という命題においては、“重度化対応”や“看取りへの支援”が避けられない課題となっている。
グループホームにおける終末期支援については、これまでにもさまざまな調査研究事業や事例検討などが行われてきたが、事業所の対応状況や認識はまちまちで、重度化した時の退居要件にも格差がある。
本調査研究事業は、より多くのグループホームが終末期支援の実践に結びつけていけるように、医療連携、職員体制、スタッフの技術向上、また、事業所そのものの健全かつ継続的な経営を保障する制度的な支援・整備など、様々な角度からの検証を行い、個々の利用者の「初期から終末を支える地域密着型サービス」として、グループホームケアの方向性を再確認するものである。
認知症グループホーム事業実態調査・研究事業
本調査研究は、根拠に基づいたグループホーム業界全体の実態把握と構造分析が急務であることから、平成17年度より全国認知症グループホーム協会会員事業所に対するアンケート調査を基本に実施している。
調査結果は、ケアの質の向上、経営環境、労働環境などを確保するための基礎データとして活用し、より質の高いサービス提供体制づくりのための経年的な調査とすることを想定している。今年度の調査内容は昨年度の調査項目を基本としつつ、平成18年度からはじまった医療連携体制加算や運営推進会議、多機能化への動き等、改正介護保険制度の新しい取組みにも注目している。
また、介護報酬改定などで事業所経営に及ぼされた影響等の把握も行う。